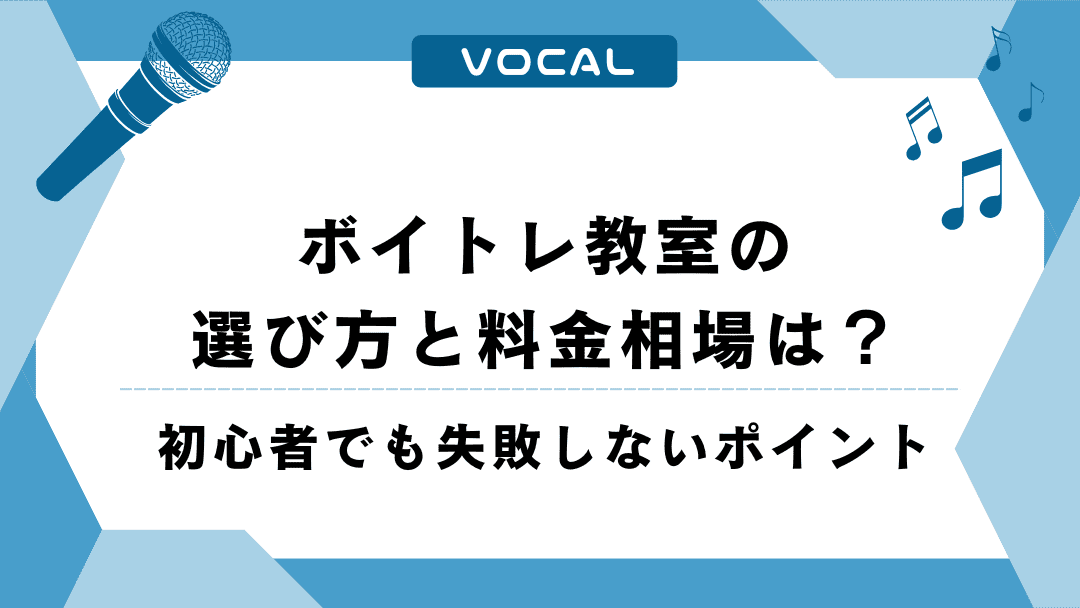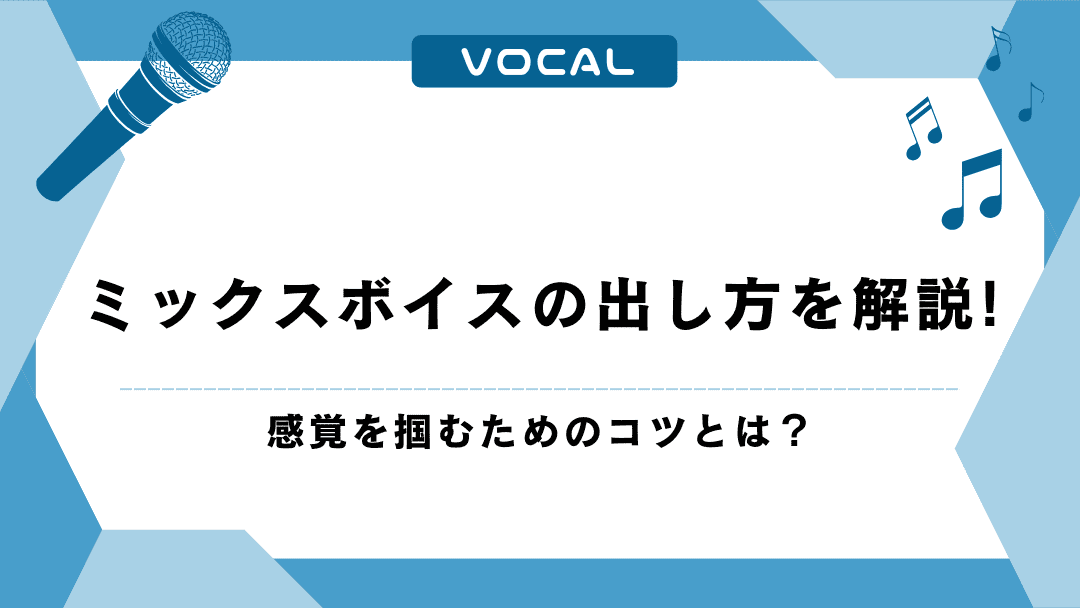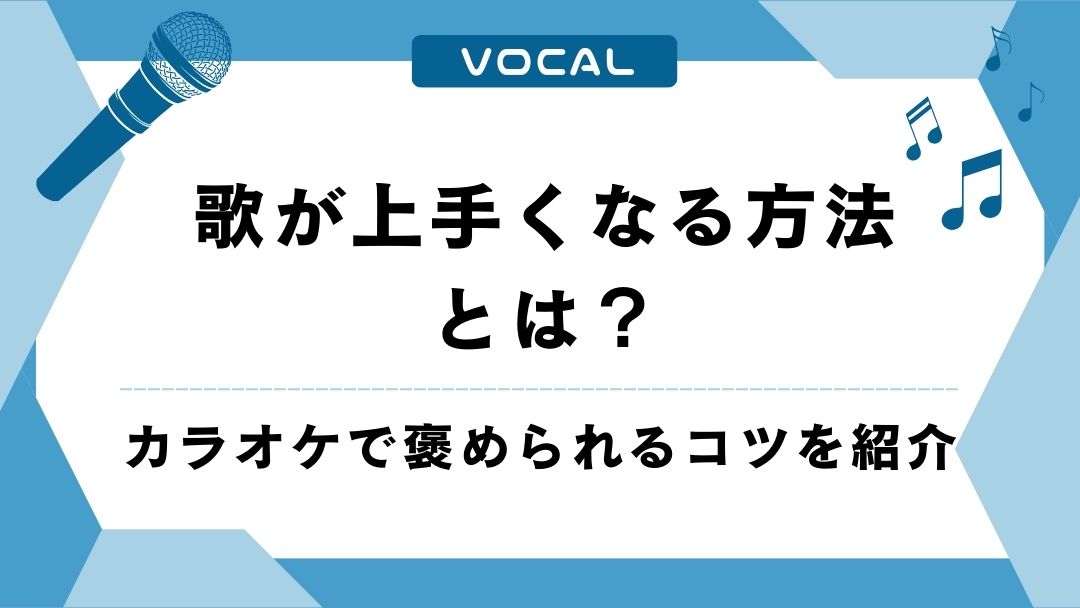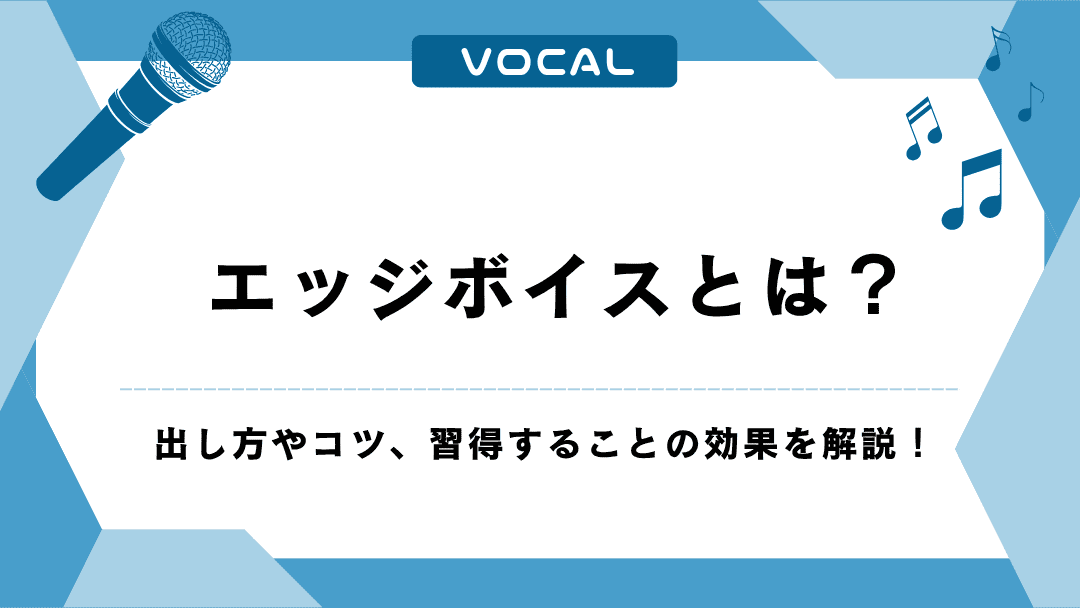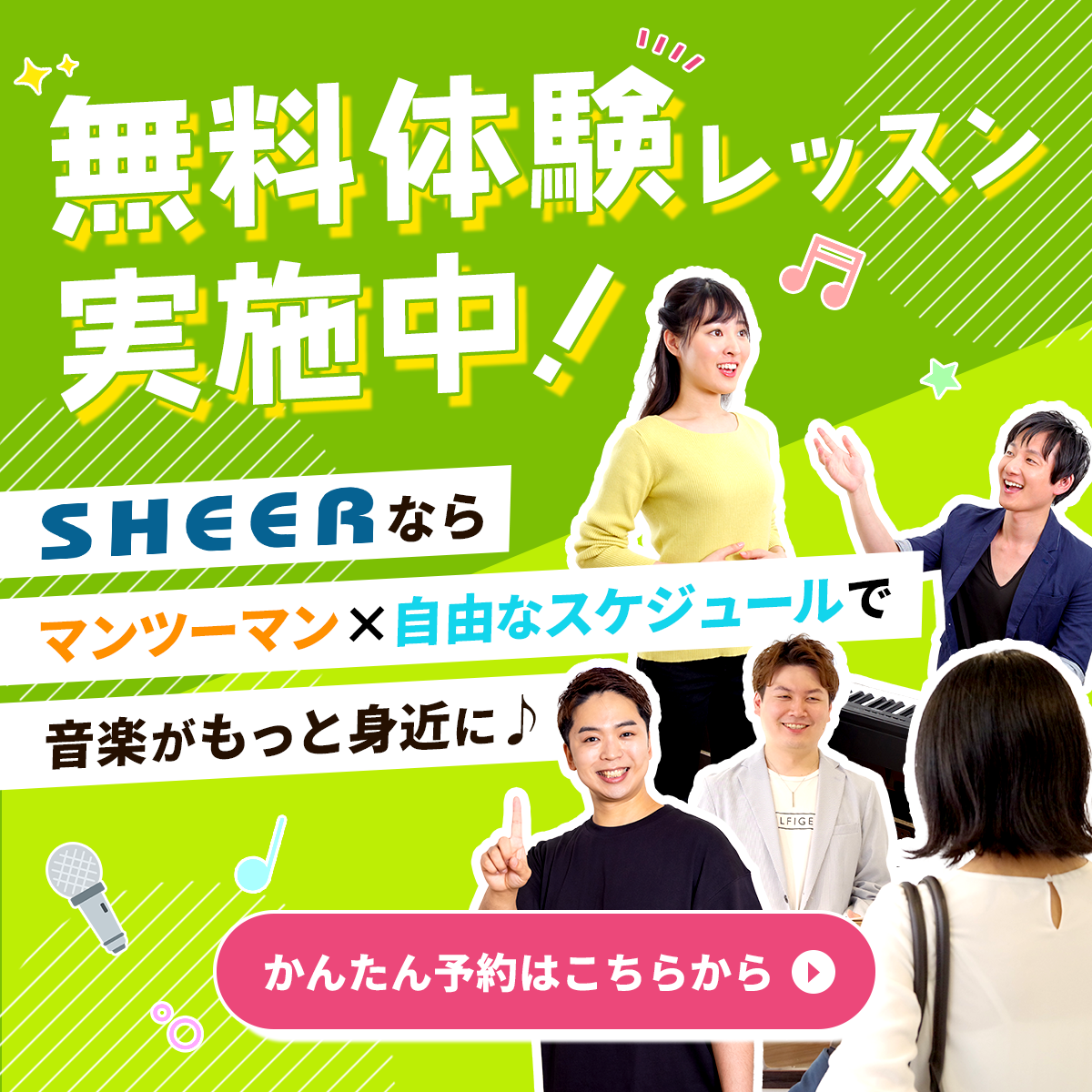がなり声の出し方とは?おすすめの練習曲や注意点を解説!

迫力ある歌い方を身につけたいなら、がなり声は非常に効果的なテクニックです。
声にかすれや荒々しさを加えることで、感情をより伝えやすくなり、聴く人の心に響く歌声が生まれます。
ただし、がなり声を出す際、間違った発声を続けると喉を痛めるリスクがあるため、正しい方法を理解したうえでの練習が欠かせません。
この記事では、がなり声の特徴や出し方、練習に適した曲・注意点などをわかりやすく解説していきます。
目次
がなり声とは?

がなり声は、声帯のすぐ上にある仮声帯を意図的に震わせ、声にかすれやノイズを加える発声法です。
ロックやアニソンといった、感情豊かな表現が求められる音楽ジャンルで多用されていて、歌声にアクセントを加え、聴く人に迫力や緊張感を強く印象付ける効果があります。
このテクニックを習得すれば、楽曲に深い感情を乗せることができ、表現の幅を大きく広げられます。
しかし、誤った方法で練習を続けると、喉へ大きな負担がかかる危険性があるため、安全に習得するには段階的な練習が欠かせません。
がなり声とシャウトの違いは?
がなり声とシャウトは、どちらも歌声に力強い感情を込める発声テクニックですが、そのアプローチは明確に異なります。
がなり声は、通常の歌声に仮声帯の振動を加え、かすれたような音を意図的に生み出す発声法です。
地声やミックスボイスと組み合わせることで、特定のフレーズに荒々しさや深みを加えられ、表現の幅が広がります。
対照的に、シャウトは叫ぶように声を張り上げ、音程よりも勢いや爆発力を重視する発声法です。がなり声が音程と感情を両立させた表現方法である一方で、シャウトは激しい感情をストレートにぶつけるような表現に向いています。
3ステップで解説!がなり声の出し方

がなり声を安全に習得するためには、段階を踏んで練習することが不可欠です。
急に力んで発声すると、喉を痛めるリスクが高まります。
そこで、初心者でも無理なく取り組めるよう、がなり声の基本的な出し方を3つのステップで解説します。
段階的なアプローチによって仮声帯を使う感覚を少しずつ身につけ、喉への負担を抑えながら力強い発声を目指しましょう。
①仮声帯を閉める感覚を覚える
がなり声を出すためには、仮声帯をコントロールする感覚を身につけることが重要です。
仮声帯は声帯のすぐ上にある膜のような組織で、通常の発声では使われませんが、意識して閉じることで、がなり声独特の響きを生むことができます。
「ンッ、ンッ」と軽く咳をするように繰り返すと、仮声帯が閉じる感覚をつかみやすくなります。
最初はコントロールできなくても問題ないので、喉の奥が閉まる感覚を少しずつ意識しながら、練習を重ねていきましょう。
②咳払いの状態で声を出す
仮声帯を閉じる感覚を覚えたら、その状態のまま音を乗せて「あぁ」と短く声を出してみてください。
「あ゛ぁ」と濁音が付いたような音が出たら、がなり声に近づいています。
この際、喉に余計な力を入れないように意識することが重要です。
力任せに声を出すのではなく、咳払いに声を乗せるような感覚で、少しずつ音に荒さを加えていきましょう。
③そのまま咳払いを伸ばしてみる
咳払いに声を乗せて発声できるようになったら、そのまま息を長く吐き出すように声を伸ばしてみましょう。
「あー」と声を出しながら、咳のときの喉の使い方をキープすると、声に自然なかすれや唸りが加わり、がなり声らしいニュアンスが生まれます。
このときにも、無理に声を張り上げないことが重要です。
短時間の練習から始め、喉に違和感があればすぐに休むようにしましょう。
がなり声が特徴的な楽曲5選

がなり声を練習する際は、実際にその表現が使われている楽曲を参考にするのが効果的です。
曲のなかでがなり声がどのように使われているかを聴き取り、自分の歌い方に取り入れていくことで、実践的な技術が身につきます。
以下では、がなり声の使い方が印象的な人気楽曲を5曲厳選しました。
ジャンルやアーティストの個性によって表現の幅が異なるため、まずは自分の声に合うスタイルを見つけるところから始めましょう。
Ado「うっせぇわ」
Adoの「うっせぇわ」は、がなり声を使った感情表現が際立つ楽曲として有名です。
サビやフレーズの一部で声に強いかすれを加えることで、怒りや反抗心が伝わり、楽曲の世界観をより深く印象づけています。
特に「正論はどっち?」などのフレーズでは、がなり声による鋭いアクセントが効果的に使われています。
女性ボーカルでも迫力あるがなり声を披露している好例であり、模倣しやすいポイントも多いため、初心者にもおすすめです。
モーニング娘。「シャボン玉 」
モーニング娘。「シャボン玉」は、アイドル楽曲としては珍しく、がなり声が積極的に取り入れられた一曲です。
曲全体で感情の起伏が激しく、サビでは声にざらつきや荒さを加えたがなり声が使われています。
なかでも「愛する人はあなただけ」といった力強いフレーズでは、仮声帯を震わせた発声が特徴的です。
アイドルソングであっても、がなり声を通じて感情表現の幅が広がることを実感できる一曲です。
ONE OK ROCK「完全感覚Dreamer」
ONE OK ROCKの代表曲「完全感覚Dreamer」は、英語と日本語を織り交ぜながら、がなり声やシャウトを巧みに使いこなす高度なボーカルテクニックが詰まった楽曲です。
とくにイントロからサビにかけては、ボーカルのTakaの声に強い荒々しさが加わり、エネルギッシュな印象を与えています。
がなり声を取り入れる際の強弱のコントロールや、地声との切り替えのタイミングなど、練習において参考となる要素が豊富に含まれる一曲です。
クリスティーナ・アギレラ「Fighter」
クリスティーナ・アギレラの「Fighter」は、ソウルフルで力強いがなり声が随所に登場する洋楽の名曲です。
彼女のがなり声は、荒々しさだけでなく、音程やリズムの正確さも兼ね備えており、楽曲にダイナミックな表情を加えています。
とくにサビでは、地声と仮声帯を組み合わせたような絶妙なバランスで声を響かせており、非常に高度なテクニックが求められます。
洋楽で本格的ながなり声を学びたい方にとっては、非常に参考となる一曲です。
みきとP feat.鏡音リン「ロキ」
ボカロ曲「ロキ」は、みきとPによるエネルギッシュなナンバーで、がなり声の要素が多く含まれています。
鏡音リンの声には独特の張りがあり、ところどころに強めのかすれた発声が見られるため、がなり声のニュアンスを掴むのに役立つ一曲といえるでしょう。
人間が歌う場合も、この曲のテンポやリズムに合わせてがなり声を取り入れて練習することで、自然な切り替えのタイミングや息継ぎのコツを体得しやすくなります。
がなり声を出すときの注意点

がなり声は歌に迫力を与える効果的なテクニックですが、間違った出し方をすると、喉を痛めたり、聞き手に違和感を与えたりする恐れがあります。
発声の仕組みが特殊であるがゆえに、十分な知識と注意が必要です。
とくに、がなり声は感情を強調するために使われるテクニックなので、使いどころや頻度を誤ると歌全体の印象を損なうこともあります。
安全かつ効果的に活用するために、以下の注意点を意識して練習しましょう。
多用しすぎず、強調した部分にだけ入れる
がなり声はインパクトが強いため、多用すると楽曲全体が単調になり、聞き手に不快感を与える可能性があります。
「感情が高まるポイントや歌詞を強調したい部分に絞って使うことで、効果的なアクセントになります。
とくにバラードやポップスでは、静と動のコントラストが重要なため、がなり声を入れる位置を慎重に選ぶ必要があります。
使いすぎず、曲の盛り上がりに合わせて一部に取り入れるのが理想的です。
喉を痛めないよう少しずつ練習する
がなり声は喉に負担のかかる発声法であるため、無理に練習を続けると声帯や仮声帯を傷めるリスクがあります。
特に初心者の場合、正しい出し方を身につけないまま力任せに声を出すと、炎症やポリープの原因にもなりかねません。
練習は1日10分程度から始め、喉の状態に注意しながら徐々に発声時間を延ばしていきましょう。
痛みや違和感を感じた場合は、すぐに練習を中断することが重要です。
がなり声を正しく習得するにはボイストレーニングを受講しよう!

がなり声を正しく習得したいと考えるなら、独学よりもプロのレッスンを受講することが効果的です。
仮声帯を使った発声は通常の歌唱とは異なり、無理な発声を続けると、喉への負担が蓄積しやすくなります。
独学では「正しい音が出ているのか」「力みすぎていないか」などを見極めるのが難しく、気づかぬうちに喉を痛めてしまうこともあります。
本格的にがなり声を習得したいという方や、効率よく歌のテクニックを身に付けたいという方は、シアーミュージックのボイストレーニングがおすすめです!
シアーミュージックではマンツーマンのレッスンを開講しており、個々の声質や筋肉の使い方を見極めたうえで、無理のない練習方法を提案しています。
安全かつ効率的に歌唱テクニック習得を目指したいという方は、ぜひ一度シアーミュージックの無料の体験レッスンにお越しください!
体験レッスンを予約するがなり声の出し方を解説 | まとめ
がなり声を正しく使うことで、歌声に力強さや感情の深みを加え、聴く人の心を揺さぶるようなインパクトを与えられるでしょう。
しかし、仮声帯を使う特殊なテクニックゆえに、誤った方法で練習すると喉を痛めるリスクも伴います。
今回紹介した3つのステップや注意点を意識しながら、少しずつ練習を進めることが大切です。
また、より安全かつ効率的にがなり声を習得したい方は、プロのボイストレーナーによるレッスンの受講がおすすめです!
自分の声に合った指導を受けながら、表現力のある歌声を目指しましょう。